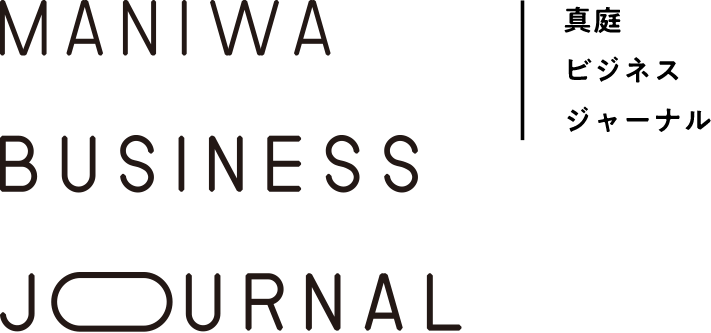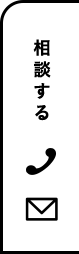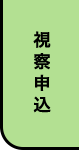地域の資源を
未来につなぐ。

真庭木材事業協同組合
代表理事組合長 筏孝生
2005年の市町村合併でできた真庭市は、県内で最大の面積を誇り、そのうちの8割が森林という、まさに“木のまち”だ。豊富な地域資源である山、そこから出る木を時代に合わせて利用し、地域の基幹産業として発展させてきた。
「うちの組合は1950年に設立して、今は50数社が株主となって構成しています。昔は、製材や材木よりも山から出る燃料として炭の需要があり、それを売るところから始まったと聞いています。それから材木に変わり、15年前からはチップ製造に主軸を移してきました」 そう話すのは、筏孝生さん。この地で101年前から木にまつわる仕事をしてきた中国林業の2代目社長であり、3年前から真庭木材事業協同組合の組合長を務める。「私は兵庫の生まれですが、祖父が立ち上げた会社を継ぐために、高校卒業して真庭に来ました。18歳から製材のことをやってきましたわ(笑)。祖父は亡くなる1年前の102歳まで社長をした元気な人で、この辺りには創業100年くらいの会社がたくさんありますよ」 長い歴史の中で人から人へと受け継がれてきた、真庭市の木材事業。筏さんの言葉にはその矜持が滲む。
林業や木材事業という産業自体が厳しい時期もあった。外国産材が増えたことなどから1980年代からは木材価格が低下。1992年の中国道開通でも産業の低下に危機感を覚えたところから、間伐材や製材端材を燃料とするバイオマス発電事業を市として取り組んだことが大きな転機となった。
「2009年にバイオマス集積所、2015年にバイオマス発電所ができ、取り巻く環境がガラッと変わりました。それまでつくっていたチップは製紙会社に売っていましたが、発電所の燃料供給につなげる流れができた。集積所に集まるものは、①樹皮②枝葉や竹③市場に出せない丸太の3種類。我々が一番困っていたのが製材で出る木の皮でした。産業廃棄物として処理代がかかっていたものが、逆に有価物としてお金になるし、山師も伐倒の際に出る枝葉はそれまで山に捨てていたけど、それもお金になる。そりゃ、大きいことですよ」同組合が発電所に供給するチップの量は、平均して1日200トン以上、多い時は1日に300トンにもなる。組合の売上もこの10年で1〜2億円から9億円まで増えた。チップを自社で生産できる大型機械を持っていない製材所でも、組合で一括してできるため業界全体で経営の安定化につながっている。
地域資源と経済がうまく循環する流れができ、今や“木のまち”は「バイオマス産業都市」として全国に名を轟かせている。それでも、筏さんは未来を見据え、気を引き締めている。 「バイオマス発電所も全国各地にできていて、チップの安定供給ができずに倒産している発電所もある。木を余すことなく使って環境のことも考えた行動だから良いのに、地域内でうまく回らないから海外からチップを買ってそれを使うとか、本末転倒になってしまった話も聞いたことがある。そうならないためにも安定供給をし続ける体制づくりが大切で、組合として山を購入し、森林計画を立てながら経営していくことも考えています」
変化に対応しながら、地域資源を守ってきた。だからこそ、もう一つ気を揉んでいることがある。それは次世代に繋いでいくこと。昨年、真庭市内で生まれた子どもの数は約170人。高校進学も市外に出る人もいて、全体の60%は高校卒業後には市内から出てしまう。そういう厳しい状況をなんとかしたいと、高校再編の会議にも出席している。 「やっぱり何かに特化したことを学べる学校があってもいいと思うんです。真庭市が進めているバイオマス発電、木材のこと、設計のことを学べる特殊な学校を作らんといけません。こないだ大阪・関西万博にいきましてね。あの木造建築の大屋根リングのところで寝そべって天井を見ている人もいるんですわ。やっぱり木というのは、それだけ人間の心に影響を及ぼすものなんだなと思いました」産業自体をいかに持続化していくか。
そんな大きな課題に、組合としても、自分自身としても何ができるかを問う。集積地に山のように積み上がった木材やチップを前にして、力強く前を向く。
「時代は変わり、人は減っていくかもしれないけど、ここには木がありますから」